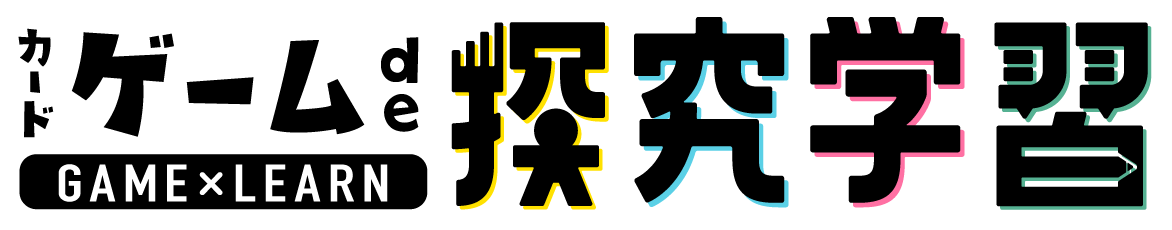【事例インタビュー】ビジネスゲームで生徒の自己肯定感・自己効力感を育てる、将来について考えられる授業をつくりたい(京都市立紫野高等学校)
学校名:京都市立紫野高等学校
業種 :教育機関
学科 :普通科・アカデミア科
生徒数:840名
本稿では、ビジネスゲームを学校の授業で活用した事例をご紹介します。
京都市立紫野高等学校(以下、紫野高校)の1年生を対象とした公共の授業の中で、7種類のビジネスゲーム(2030SDGs、SDGs de 地方創生、SDGs アウトサイドインビジネスゲーム、働き方改革ゲーム、The 商社、The Engineers、地域共生社会)を年間を通して活用いただいた事例です。
はじめに先生への単独インタビューの内容をお届けし、その上で、6名の生徒を交えた座談会の様子をお届けします。
紫野高校のプロフィール
※ユネスコスクール…ユネスコ憲章に示された理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校。ESDの推進拠点としての位置づけもある。
先生へのインタビュー
京都市立紫野高等学校 教諭
小林 孝由 様

生徒が活発に意見を言えるような、楽しく学べる環境をつくりたい
―生徒の自己肯定感や自己効力感に課題意識をお持ちであるとお聞きしています。それはなぜでしょうか?
小林先生:生徒たちが失敗を恐れずに活発な意見交換をすることで、楽しく学び、それを深められるような環境になって欲しいと思っているからですね。
日本財団が2019年に行った「18歳意識調査」の国際比較、内閣府の2019年度「子ども・若者白書」、ユニセフの2020年「幸福度調査」。そういった調査資料の中では日本の中高生の自己肯定感・自己効力感の低さが明らかになっています。紫野高校で行ったアンケートでも同様の結果となりました。
実際、私自身の経験においても、授業中に「これについてどう思う?」と聞いても反応が薄いと感じることが少なくありません。生徒からすると、挙手をして意見を述べることに対して「馬鹿にされないか」「頭が悪いと思われないか」と考えているのかもしれません。私はそんな状況を打破し、生徒たちが活発に意見を言えるような、楽しく学べる環境をつくりたいと思っています。
そして、そのためには、OECDの Education 2030プロジェクト(※)において提唱されているように、当事者意識と、その土台となる自己肯定感や自己効力感の養成が重要だと考えています。
※Education 2030プロジェクト…2030年という近未来において子供たちに求められる能力の検討と、そうした能力の育成につながるカリキュラムを検討していくもの。
ビジネスゲームを教材として選ぶ際の3つの基準
―今回、授業にビジネスゲームを活用された背景を教えてください。
小林先生:生徒の自己肯定感や自己効力感の涵養に効果的な教材を探していた時に、大学生や社会人を対象にしたビジネスゲームの効果に関する論文を発見したことがきっかけです。
論文では「PDCAサイクルの実施能力」「グループディスカッション能力」「プレゼンテーション能力」などの向上が報告されており、これらの能力の向上が生徒の自己肯定感や自己効力感を養うのではないかと考えました。
―ビジネスシーンにおいても、個人の能力の向上は自己肯定感や自己効力感を養うと言われているので納得です。ちなみに、ビジネスゲームを教材として選ぶ際の基準はどのようにお考えでしたか?
小林先生:そうですね、私の中で基準は3つありました。
1つ目は「経済活動や社会活動における成功・失敗体験の経験を短時間で繰り返し獲得できるゲーム」であること。2つ目は「自分一人の行動がチームの仲間や他のチームに影響を与えて、その影響が全体に広がるようなゲーム」の体験を通じて自身の行動で周囲を変えられる感覚を掴めること。3つ目は「現実世界を可能な限り反映したゲーム」の体験によって現実社会の仕組みを理解できることです。
―かなり具体的な基準ですね。
小林先生:これは、私自身がカードゲーム「2030SDGs」のワークショップを受講した経験が影響しています。この3つの基準はまさにカードゲーム「2030SDGs」の体験によって私が感じたことですね。
カードに書かれている1つ1つの情報が全てどこかでつながっていて、自分の行動次第でそれらの持つ効果が変わっていくという体験は衝撃的でした。高校で政治や経済を教えている私としては、このゲームはまさに生徒に体験してほしいことそのものでした。
―プロジェクトデザインのビジネスゲームを知ったきっかけがカードゲーム「2030SDGs」だったのですね。
小林先生:その通りです。カードゲーム「2030SDGs」のことを調べる中で、ゲーム開発に携わっていたプロジェクトデザインのことを知りました。そしてプロジェクトデザインの開発した様々なビジネスゲームのワークショップに参加し、授業に取り入れることができそうなゲームのファシリテーター養成講座を受講しました。
―その節はありがとうございました。
ビジネスゲームを授業で活用するために行ったこと
―紫野高校ではビジネスゲームを1年生約80人を対象に、年間を通して授業に取り入れているとお聞きしています。生徒にとってビジネスゲームは馴染みがないものだと思うのですが、「これからビジネスゲームをやるぞ!」という際にどのような説明をされましたか?
小林先生:私は、生徒がゲーム内で失敗と成功の体験をする中で「責任ある行動をとる力」「対立やジレンマに対処する力」「新たな価値を創造する力」を身に付け、社会の中でたくましく生きてほしい、社会を照らす人になってほしいと思っています。
そこで、いきなりビジネスゲームをやるのではなく、まずは「学校は何のために存在するのか」「どのように生徒に成長して欲しいのか」ということを伝えました。
具体的には、学校とは平和な社会を実現するために求められている能力を身に付ける場であること、そのために、現実世界を模したシミュレーションゲームの中で頭の中の知識を使ってみることが大切であるという話をしました。
―なるほど。生徒にとって身近な「学校」の存在意義とビジネスゲームを実施する目的との関連性を生徒に伝えたのですね。とても分かりやすい説明だと思います。ビジネスゲームを授業に取り入れる上で工夫されたことはありますか?
小林先生:事前資料ですね。これは、授業で実施するビジネスゲームがどんなゲームなのか、どういったコンセプトをもとにつくられたものなのか、ゲームで使用するカードはどのような内容なのかを記した資料です。
生徒のやる気や興味関心の方向はさまざまですから、生徒の好奇心や探究心を育てるためにも、生徒が興味を持ったものを深堀りできるような事前資料をつくり、配布するようにしました。
―実際にビジネスゲームを授業に取り入れ始めた頃の生徒さんの様子はいかがでしたか? ビジネスゲームはチームで取り組む内容になっているので、チームワークの難しさに戸惑う生徒もいらっしゃったのではないかと思います。
小林先生:確かに、ビジネスゲームを活用した授業を始めた当初は「話に入りたくても入れない」「自分に自信が持てずに他の人に全部任せてしまった」という生徒がいました。
そこで、消極的な生徒に声をかけたり、皆の意見を聞きながら「チームの人数を減らして発言しやすくする」「議論時間に1人1回は必ず話すグランドルールを設ける」などのルールを改善していきました。そういった中で、ゲームに積極的に関わる生徒が徐々に増えていったと記憶しています。
―生徒がビジネスゲームに慣れていく中での変化はありました?
小林先生:生徒たちが事前準備の質がゲームの勝敗を分けていると気づき始めて事前資料を熟読するようになりました。また、チームを固定せずに、毎回チームを変えていくことで、準備が上手い生徒たちが、そうでない生徒たちに教えるようになって、良い影響が全体へと広がっていきました。
ビジネスゲームを体験した生徒に起きた変化
―ビジネスゲームを通して、生徒たちの自己肯定感・自己効力感の変化にはどのようなことがありましたか?
小林先生:ゲーム体験後に行ったアンケートの結果からは、自己肯定感や自己効力感の確かな向上が見受けられました。また、「次回はこんなことにチャレンジしてみたい」という言葉が多く見られるようになり、実際に授業でもそのように行動している生徒が多くいました。
例えば、グループの中でリーダーに頼っていた生徒は、ゲームの回数を重ねるごとに自発的に行動できるようになっていましたし、独りよがりだった生徒が、周りの生徒を頼ったり意見を聞くことができるようになっていました。
―生徒さんそれぞれにポジティブな変化があったのですね。その変化が何かの結果につながった出来事などはありますか?
小林先生:そうですね、ビジネスゲームの効果かどうかは不明ではありますが、ゲームを体験している2クラスの学校行事での成績が突出してよかったです。百人一首大会や体育祭の1年生対抗など、その2クラスには賞状がたくさん飾られていますね。私としては、クラス内の関係の質を向上させ、思考や行動、結果の質を高めるという正の循環に、ビジネスゲームの効果が発揮された可能性はあるのではないかと思っています。
―生徒さんの変化について保護者の方からご意見などはありましたか。
小林先生:保護者の方とお話をした際に「子どもが授業でやったゲームのことや、その時に頑張ったことを家で語ってくれました。中学生のころに比べて生き生きと学校に通うようになって、本当に学校に感謝しています」と言ってくださったことがありました。
―それは嬉しいですね! 今回のインタビューを通じて、ビジネスゲームを活用することで、学校の授業の中でさらなる学びの場を作られていることがよく分かりました。
生徒を交えた座談会
京都市立紫野高等学校 教諭
小林 孝由 様
京都市立紫野高等学校1年生
井上 遥(いのうえ はるか)さん
川端 萌生(かわばた めい)さん
錦織 知可(にしこおり ともか)さん
問山 遼太郎(といやま りょうたろう)さん
植田 真尋(うえだ まさちか)さん
大崎 仁徳(おおさき ひとし)さん

井上さん「ゲームをする前は働くことに対してパソコン作業などの個人仕事のイメージが強かったです。しかし、想像していたよりもコミュニケーションが重要なのだと気づきました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
井上さん:私は今まで授業でゲームをすることがなかったので不安でした。授業形式が変わって、授業が動画になると聞いて、ズボラな私はちゃんと勉強できるのか不安でした。しかしゲームをやっていくうちに、その中に学びがあることに気づいてからは安心して授業に参加できています。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
井上さん:私はゲームを通して疑問に思ったことがありました。クラスの中で交渉の役割をしていると、どんどん相手のことが分かって慣れてきてしまい、現実の社会より簡単になっている気がします。他のクラスなど、知らない人とやった方が実践に近いと思うのですが、なぜやらないのかが疑問でした。
―生徒さん同士でお互いを理解することができているのですね。この疑問に対して小林先生はどうお考えですか?
小林先生:まずはクラスという安全な場所で生徒自身の可能性を育て、生徒たちで誰1人取り残さない教室を実現してほしいと考えていました。なので知らない人とやりたい、外に出たいと思ってくれるのはある意味卒業の時期だと思います。皆が能力を身に付けて社会に出て欲しいですね。
―ありがとうございます。ではビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
井上さん:ゲームをする前は働くことに対してパソコン作業などの個人仕事のイメージが強かったです。しかし、会社間で取引をしたり、チームでの話し合いが多く、想像していたよりもコミュニケーションが重要なのだと気づきました。
私は歴史が好きで、歴史関係の職に就きたいと考えています。将来、人に物事を説明する時にコミュニケーション能力は役立つと思いますし、それをゲームで養えるのはとても良いと思いました。
川端さん「今までは、なぜ小学校の先生になりたいのか自分でも分かりませんでしたが、ゲームを通して気づくことができました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
川端さん:私は小林先生の授業が好きでした。なのでゲームをすると聞いて先生の授業が受けられなくなるのが寂しかったです。あとは授業形式がゲームになってしまって、勉強についていけるのかが不安でした。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
川端さん:今回体験したゲームはどれも一人ではできないもので、同じチームで協力し合ったり、全員の知恵を出し合って1つのものを完成させるという経験ができたと思っています。私はこういった経験は公共に限らず、学校生活にも活かせると考えていて、授業を通して可能性が広がったように感じました。
―ビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
川端さん:私は小学校1年生の頃から小学校の先生を目指しています。今までは、なぜ小学校の先生になりたいのか自分でも分かりませんでしたが、ゲームを通して気づくことができました。私は人と関わることが好きで、人と話したり、その人の良いところを見つけることが好きだから小学校の先生になりたいのだとわかりました。
それまでは自分のことを一番分かっているのは自分だと考えていましたが「自分が知っている自分」と「相手が知っている自分」というのは違うと気づきました。また、その違う自分を合わせることによって新しい自分が生まれると先生に教えていただき、その通りだと思いました。
錦織さん「私はゲームの中で自分から動いて交渉をしに行くことが多く、自分は動くことが好きなんだと気づきました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
錦織さん:私は小林先生の授業が面白くてとても好きだったので、先生が持ってきたゲームなら面白いだろうと思っていました。ただゲームは楽しみでしたが、自分の負けず嫌いなところが悪い影響を与えないか不安な部分もありました。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
錦織さん:ゲームを通して自分に対する理解が深まりました。私はゲームの中で自分から動いて交渉をしに行くことが多く、自分は動くことが好きなんだと気づきました。そこから、将来は営業職に就くのも良いかなと、自分の未来についても考えるようになりました。
また、私は勉強をする理由は自分の可能性を広げるためだと考えています。将来なりたいものができたときに対応するための準備だと考えていて、その点では今回のゲームの体験も様々な経験があって将来につながっていると思います。
―ビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
錦織さん:社会に出ることに対して不安はありますが、日常生活でゲームの中の経験を活かせた時は他の人より1歩リードした感覚を持つことができました。実際の社会は複雑で矛盾もあると思っているので、その矛盾の中で自分がどう動いていけばいいのかを高校3年間で学んでいきたいです。
問山さん「ゲームの中で学んだものが実際の社会にある出来事だと気づくことで、自分の視野が広がる感覚がありました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
問山さん:最初に聞いたときは授業でゲームをするというのがあまり想像できなかったです。でも、中学までの社会の授業をプリントと教科書で行っていたのに対して、ビジネスゲームでは実際の社会を体験できると聞いてワクワクしました。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
問山さん:ゲームを通して自分や相手の特性を理解することができました。僕はディスレクシアという特性を持っていて文章を読むことが苦手でゲームが上手くできないのではないかと思っていましたが、チームの中に様々な役割があったので、チーム内で苦手な部分を補いあうことができました。自分や相手の苦手なことを補うために必要なことは何か、考えることが大切だと気づきました。
また、ゲームの中で学んだものが実際の社会にある出来事だと気づくことで、自分の視野が広がる感覚がありました。
―ビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
問山さん:僕はゲームを通して経営や交渉、分析など様々な役割を経験しました。そこから、自分はどの役割でも自由に動きたいのだと気づき、将来は自分のやりたいことをすぐに行動に移せるような職業に就きたいと思いました。
植田さん「社会はもっと複雑で、ゲームのようにお互いを思いやりながら行動していくことは難しいのではないかと考えました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
植田さん:僕も中学の頃に行っていた教えられたことをノートに書くような授業が嫌いだったので、ビジネスゲームをやると聞いて嬉しかった記憶があります。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
植田さん:ゲームに対する熱量が人によって違うことに気づきました。そして、その違いは「何のために勉強するのか」が人によって違うからだと考えています。なので学校で「何のために勉強するのか」を考える機会をつくって欲しいと思いました。考えることで人によって違う部分に気づき、違いを認め合えたら良いなと思っています。
―ビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
植田さん:僕は、社会に対する十分なイメージはできていないです。どんな形で人生を全うするかを考えたとき、社会はもっと複雑で、ゲームのようにお互いを思いやりながら行動していくことは難しいのではないかと考えました。
―ではその複雑な社会の中で、植田さんはどのような立場になりたいですか?
植田さん:将来はファシリテーターになりたいと思っています。お互いの自分らしさを認め合えるように社会をファシリテートして、世界と人々と自分自身が豊かになることを目指しています。
大崎さん「今まで分からなかった自分の良い面も悪い面も知れた気がしました」
―先生から初めてビジネスゲームをすると聞いたときに感じたことはありますか?
大崎さん:僕は授業が映像授業になることに反対でした。社会の授業は物語やその流れが大切だと考えていて、小林先生の授業は僕の中の物語に対していろいろな情報を加えてくれるのがとても面白いと感じていました。なので動画になってしまうと先生やクラスの皆から受け取れる情報も減り、学びが薄くなるのではないかと思っていました。
―実際に授業でゲームを受けてみてどうでしたか?
大崎さん:最初は、ゲームを通して社会の知識を深めるという感覚が分かりませんでした。どちらかというと協力や競争といった人間力の方が重要視されている感覚があり、社会に関する知識は副題のように感じました。ゲーム後の振り返りの内容も、リーダーシップや交渉力など自分の行動にフォーカスされていて、僕のイメージした公共の授業とは違いました。
しかし、ゲームを体験していくうちに公共の学びも確かにあると感じ、テストやニュースを見たときにその知識と結びつく場面がありました。また、得意不得意に関係なく色々な役割に挑戦してみようと先生に言われて、僕も色んな役割をやりました。初めてリーダーをやったときは上手くいかず終わることもありましたが、次にリーダーをやったときに他の班を見てきた経験から混乱しているチームをまとめることができて、今まで分からなかった自分の良い面も悪い面も知れた気がしました。
―ビジネスゲームを体験して、自分が働くことや将来の社会への関わり方について何か変化はありましたか?
大崎さん:僕は自分のコミュニケーション能力が低いと思っています。そして社会は人の集まりだと考えているので、将来生きていくのに苦労すると思っていました。
しかし、ゲームを体験したとき、どの役職でも自分の良いところが必ず1つは見つかっていて、反省が多い場面でも自身に対する気づきが得られていました。人と人とが関わるゲームの中でこうした気づきが得られたことは、将来に対する自信にもつながりましたし、社会に出てもやっていけそうだと希望になりました。
小林先生「生徒たちが将来について考えられる授業をつくりたい」
―今後もビジネスゲームを使用した授業を行う予定はありますか?
小林先生:はい。この活動は今後も継続していきたいと考えています。生徒たちにどのような力が身についたのか、自分の強みは何なのかを可視化して、将来について考える際のヒントを提供できるような授業や振り返りを構築したいですね。
―紫野高校の取り組みを今後も応援しております。本日はありがとうございました!
参考情報
紫野高校のHPに、ゲーム体験の様子をご紹介いただいています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
・1年生「公共」の授業~経営を学ぶワークショップ~|京都市立紫野高等学校
・1年生「公共」の授業~あなたは新製品の開発担当者~|京都市立紫野高等学校
・1年生「公共」の授業〜社会課題を解決するビジネスを生み出そう!~|京都市立紫野高等学校
記事制作に関わったメンバーの紹介
インタビュアープロフィール

亀井 直人
鳥取県立鳥取東高等学校卒業、福岡工業大学情報工学部情報通信工学科卒業。SE(インフラエンジニア)として長く経験を積む。プロジェクト遂行におけるチームのパフォーマンスを引き出すためにファシリテーション技術の習得・実践を続ける。特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会では役員(2016年~2021年理事、2019年~2021年副会長)を務める。富士ゼロックス福岡在籍中にSDGsとビジネスゲーム「2030SDGs」に出会う。ビジネスゲームが持つ力の素晴らしさに触れ、2020年に研修部マネージャーとしてプロジェクトデザインに合流する。活動を通じて関わり合う方々との対話を楽しみにしている。鳥取県鳥取市出身。蟹と麦チョコが大好き。
- 経済産業省認定情報セキュリティスペシャリスト
- PMP(Project Management Professional)
- NPO法人 SDGs Association 熊本 監事
- Facebookアカウントはこちら
執筆者プロフィール
浜田 葉月
神奈川県横浜市出身。神奈川県立希望ケ丘高等学校卒業、北九州市立大学地域創生学群在学。中学校時代「AOKI起業家育成プロジェクト」に参加し、社会起業家を通して社会問題に興味を持つ。大学進学を機に福岡県へ移住し、現在は公共空間の活用や地域活動を行う組織のマネジメントについて学んでいる。大学教授の勧めにより「カーボンニュートラル2050」に出会い、ビジネスゲームの持つ力に魅力を感じ、2025年からプロジェクトデザインのインターンに参加している。
編集者プロフィール
池田 信人
自動車メーカーの社内SE、人材紹介会社の法人営業、新卒採用支援会社の事業企画・メディア運営(マーケティング)を経て、2019年に独立。人と組織のマッチングの可能性を追求する、就活・転職メディア「ニャンキャリア」を運営。プロジェクトデザインではマーケティング部のマネージャーを務める。無類の猫好き。しかし猫アレルギー。
INFORMATION
ご案内
SERVICE
ソリューション
ビジネスゲームラインナップ
SITE MAP
Copyright © 2016 Project Design Inc. All Rights Reserved.